目次
はじめに:これは一つの仮説である
この記事は、私がこれまで複数のブロックチェーンゲーム(BCG)をプレイ・観察してきた中で感じた傾向や課題、そしてその中でも際立った存在感を放つ『キャリサバ(キャリア乙女サバイバー)』という国産BCGから得た学びをもとにした【個人的な考察】である。
BCGはまだ黎明期とも言える段階にあり、プレイヤーの属性やプレイスタイル、そして運営の手法もさまざまだ。私自身も一人のプレイヤーとして、時には成果を得られず離脱したこともあるし、魅力あるプロジェクトに深く関わった経験もある。そんな中で「なぜWeb3ゲームが伸び悩むのか」「どうすればBCGが持続的に発展するのか」という問いが浮かんできた。
そのヒントを与えてくれたのが、国産BCG『キャリサバ』だった。
BCG疲れしているユーザーが増えている?という仮説
BCGを取り巻く環境を見渡すと、少しずつ疲弊感のようなものが広がっているように感じる。ただし「BCGは信用できない」という極端な主張ではなく、あくまで以下のような背景からくる”プレイ継続へのモチベーション低下”があるのではという仮説だ。
マルチタスクで疲弊している?
BCGプレイヤーは基本的に「同時に複数のゲームをプレイ」していることが多い。本命の1〜2本に加えて、将来の期待やエアドロップ狙いでTelegramやLINE Mini Appなどの早期アクセスゲームに手を出すスタイルが主流だ。その結果、1本1本への集中が薄まり、どのゲームにも本気で向き合えず、次第に疲れていく――これはBCG特有のプレイスタイルがもたらす弊害だろう。
損をした経験がブレーキに?
もう一つの疲弊要因は、やはり”お金”に関する失敗体験だ。ポンジスキーム型の設計や、運営のラグプル(開発放棄)、極端なトークンの価格変動によって、資産を減らしたり一発退場したプレイヤーも一定数いるはずだ。
また、ゲーム内通貨と出金用トークンが固定レートにもかかわらず、売り圧が強すぎて結局損をした……というケースもある。こうした経験を持つプレイヤーは、次のゲームに手を出すこと自体に慎重になっているのではないだろうか。
BCGで収益を得るには、センスとスタイルが問われる
BCGの世界で「稼げるかどうか」は、単にプレイ時間や努力の量ではなく、その人の”スタイル”と”戦略”が大きく左右する。私の観察では、主に2タイプのプレイヤーが存在する。
RTA型プレイヤー:スピードと戦略で稼ぐ
いわゆる「リアルタイムアタック(RTA)」型のプレイヤーたちは、ゲームのローンチ直後から仕様や抜け道を徹底的に研究し、最短で稼げるルートを走り抜ける。X(旧Twitter)などで見かける稼げているプレイヤーは、多くがこのタイプだと感じている。
彼らはセンスもあり、資金力や時間の使い方も最適化されており、個人というよりは「チーム」で動いている可能性すらある。情報収集・行動・利益回収のスピード感が圧倒的なのだ。
トロコン型プレイヤー:楽しみながらコツコツ進める
対して、私自身も含めた「トロフィーコンプリート型(トロコン)」プレイヤーは、ゲームをじっくり楽しみながら、長期的な収益を期待してプレイするタイプだ。NFTを購入し、日々コツコツとタスクをこなしていくが、トークン価格の暴落や運営の調整不足によって、稼ぎにならずに離脱することも多い。
このタイプは、情報の分析や市場の動向に明るくなく、結果的に後手に回りがちである。
稼げなければBCGは流行らないのか?
Web3ゲームの魅力の一端は「稼げること」にあるが、それが失われれば本当にプレイヤーは離れていくのか。これは、BCGの本質を問う上で避けて通れない問いである。
確かに、明確な金銭的リターンを期待して参入する層は一定数存在し、彼らは稼げないと判断すれば早期に離脱する。これは否定しようのない事実だ。しかし、それを単純にネガティブな現象として捉えるのは早計である。
そもそも、ゲームへの課金動機は「投資」だけではない。たとえば私の知人には、パズドラに数百万円以上課金していた者がいる。その理由は、「稼げるから」ではなく、「面白かったから」である。ゲーム内ランキングで上位を目指したい、他者よりも目立ちたい、限定スキンを手に入れたいといった動機は、純粋に娯楽と承認欲求に根ざしたものであり、Web2時代から一貫してゲームの収益源となってきた。
この構造は、Web3においても応用可能である。すなわち、「ゲームが本当に面白く、プレイヤーの感情や欲望に訴えかけるものであれば、リターンが明確でなくとも人は遊び、課金する」という前提だ。BCGがこの“Web2的面白さ”を備えたうえで、さらにその一部をトークンやNFTという形で「プレイヤーに還元できる」設計になっていれば、たとえ爆発的な利益を生まなくとも、楽しみながらコツコツと稼ぐという新しい満足の形が成立する。
それは「ゲームで稼ぐ」というより、「ゲームの中で自分の熱量が正当に報われる感覚」に近い。Web2では存在しなかった「報酬付きの趣味」としてのゲーム体験——この価値を正しく伝えられれば、BCGはリターンが薄くても継続的にユーザーを獲得できるポテンシャルを秘めている。
ゲームの品質がWeb3発展の鍵を握る?
Web3ゲームという言葉が先行する中で、実態はWeb2における「面白いゲーム体験」から大きく外れているタイトルも多く見られる。ブロックチェーン技術を用いたトークンエコノミーの設計やNFTの所有権といった要素は確かに革新的だが、それ以前に「ゲームとして面白いか」は絶対的な基準として求められるべきだ。
コンシューマーゲームやSteamタイトルのように、クオリティの高いグラフィック・バランス調整・ストーリー性・中毒性のあるUI/UXなど、いわゆる「ゲーム体験の質」が伴わない限り、ユーザーの定着は難しい。Web3であっても、根本にあるのは「エンタメ」である以上、Web2ゲームのベストプラクティスを無視することはできない。
たとえば『キャリサバ』は、この点において他のBCGと一線を画している。独自の世界観とキャラクター性、コンテンツアップデートの頻度、ユーザーを飽きさせないギミック。こういった「普通に面白い」ゲームを作ることが、結果的にWeb3としての機能を強く活かす基盤になるのではないだろうか。
参入ハードルを「下げる」のではなく、「越えさせる」設計へ
BCGの入り口で立ちはだかる最大の壁――それは「仮想通貨」「ウォレット」「取引所」といったWeb3特有の概念や操作だろう。これまで多くのプロジェクトは、このハードルをいかに下げるか(=意識させずに遊ばせるか)を重視してきた。
しかし、私はここに少し違和感がある。
本当にWeb3を発展させたいなら、ハードルを単に隠すのではなく、ユーザーが「自然に越えたくなる」ような設計が必要ではないかと思う。つまり、ユーザー自身が学びながら参加し、Web3の概念に徐々に慣れていける構造だ。
たとえば、丁寧なチュートリアルや段階的な開放設計、ゲーム内通貨を通じた仮想通貨の理解など。教育的なUI/UXと魅力的な報酬設計があれば、ユーザーは「気づいたらウォレットを使っていた」という状態になり得る。
運営との距離感がファンの熱量を左右する
BCGにおいて、運営とユーザーの距離感は想像以上に重要なファクターだ。
たとえば私が過去に関わった海外BCGでは、日本アンバサダーという立場でTelegram上の公式グループに参加し、運営と直接対話をしていた。そこでは不具合や要望へのフィードバックも素早く、プレイヤーとの一体感が生まれていた。それが「このゲームに投資しても良い」「長く関わってみたい」という信頼へと繋がったことを覚えている。
一方で、大手が運営するBCGでは、情報発信が一方通行になりがちで、コミュニティに顔を出す機会も限られている。ユーザーからすれば「自分たちは運営からどう見られているのか」が分からず、熱が冷めてしまうケースもある。
『キャリサバ』はこの点でも好例だ。Discordでの開発陣の発言、ユーザーとのコミュニケーション、定期的なAMAや開発者のラジオ。こうした細かな“顔の見える運営”が、ユーザーの信頼感とファン層の厚みを支えているように思う。
Web2ユーザーをWeb3に流入させるために必要なこと
Web3ゲーム普及の障壁としてしばしば語られるのが、「仮想通貨」や「ウォレット」の存在である。しかし私の見解では、最大の障壁はそこではなく、「ゲームが面白くないこと」に尽きる。
いかにUIを洗練し、操作性を高め、参入しやすい仕組みを整備したところで、肝心のゲームが魅力的でなければプレイヤーは定着しない。Web2ユーザーはすでに多種多様な高品質ゲームに慣れており、その目は肥えている。多少の参入障壁があっても、それを乗り越えるだけの魅力がゲーム自体にあれば、プレイヤーは自ら学び、壁を越えてくる。
もちろん、最低限の整備は必要だ。モバイル対応、シンプルなUI、そして強制されないウォレット連携——これらは、初手での離脱を防ぐために重要である。
一方で、マーケティングに関しては再考の余地がある。Amazonギフト券などのインセンティブによって「ゲームに興味がない層」を一時的に集めても、その後のエンゲージメントは低く、離脱率も高い。むしろ、ゲームの魅力そのものを可視化し、SNSやプレイ動画を通じて“やってみたい”という自然な感情を喚起する方が、結果としてユーザーの質も高くなる。
これは、広告による一方的な流入よりも、共感を伴った自発的な拡散の方が信頼性が高く、ユーザーの行動を後押しする力が強いということだ。開発者は広告費をバラまくのではなく、プレイヤーの体験価値を最大化し、それを拡散したくなる仕掛けを設計する方が、長期的には遥かにコストパフォーマンスが良い。
BCGが本当にWeb2ユーザーを巻き込みたいなら、ウォレットの有無ではなく、「このゲームをやってみたいか」という根本に立ち返るべきである。
おわりに:BCGの未来は「ゲーム性」と「人の熱」にかかっている
ブロックチェーンゲームは、技術革新の象徴として注目される一方で、「ゲームとして楽しめない」「稼げない」「信用できない」というネガティブな声も少なくない。私もそのジレンマに何度も直面してきた。
だからこそ、今一度問い直したい。BCGの本質は、果たして“金”だけなのか?
『キャリサバ』のように、ゲームとして面白く、ファンが自然と応援し、運営がユーザーと向き合う姿勢を見せるBCGこそが、これからのWeb3時代のロールモデルになるのではないか。
すぐにバズらなくても、急成長しなくても構わない。じっくりと地盤を築き、ユーザーに寄り添い、ゲームの面白さで勝負できるタイトルこそが、Web3の未来を切り拓く鍵になると、私は考えている。
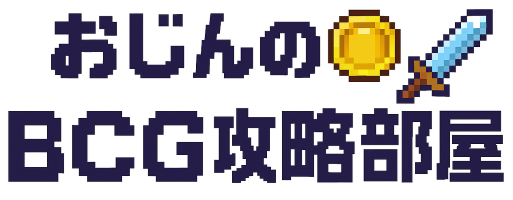
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。